
モーツァルト:アヴェ・ヴェルム
バーンスタインのモーツァルト全集が届いたんで早速聴いてます。んーっ良いですね… ってかバーンスタインってモーツァルト作品の一曲の中のきびきびした軽快さとゆったりとした重厚さの切り換えがめちゃめちゃ上手いですね… まさに自由自在、凄いです… あぁーっ私の中の「モーツァルトはベーム翁が一番神話」(笑)が、「ブラームスはベームが一番神話」に続いて崩れてゆく。。。 アヴェウ゛ェルムコルプスを序曲がわりに、エクスルターテユビラーテが始まる瞬間が「モーツァルトきたーっ」って感じで良いですね… いやぁ何だかレクイエムよか良い感じだね。通して聴くとアヴェウ゛ェルムコルプスから大ミサまで少しずつテンションを上げ、重厚さを増してゆくバーンスタインの指揮は素晴らしい、三曲通して一つの作品みたいな聴かせ方で、まるでマーラーみたいで凄い迫力です… 流石はバーンスタインですね、コーラス陣も意図をよく汲んで素晴らしい! が… しかし… 女性ソリスト二人が二人とも駄目ですね、オケに押されたのか調子悪かっのかな。シュターデは元々、声もキレいじゃないし常に調子っぱずれで速いリズムに乗り切れない(笑)こんなもんです。(クレジットにシュターデの名前を見つけて軽く落胆しました) アーリン・オジェーは始めて聴くんで調子悪いか、元々これが実力なのか解らないんだけど… 声域が狭い(一番高いところがスッキリ出ない、低い方は全然ダメ)上に、上手くない(強い所は力任せだし、弱く歌う所の音程がキープ出来てない)ちょっと酷いかなと思います。これがボニーとフォンオッターのコンビだったら最高なのにと思うと… 残念です。バーンスタインの人選ミスって事で☆一つ減点… 厳しいっすかね。

恍惚美女~聖なる処女~ 七原えり [DVD]
はっきり言って、普通に可愛いです。着エロでこんな可愛い子がぃるなんてビックリする位です。
とにかく爽やかで初々しい事この上なしって感じ!
ブログも見てますが、かなり性格もよく確かに処女かもしれないと思う。次回作もかなり楽しみですね。とにかくえりちゃん見てみんな癒されたらいいと思う。
そんな可愛い子です☆
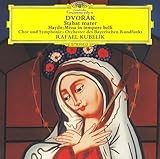
ドヴォルザーク:スターバト・マーテル
スターバト・マーテルは修道士が作った詩に曲を付けたもの。ペルコレージの作品が有名ですが、ドヴォルザークのこの曲は合唱部分が多く教会音楽の良さを感じさせてくれます。演奏がまた、なかなか素晴らしい。やはり、ヨーロッパの音楽文化は、キリスト教の教会音楽とは切り離せないもので、年中行事の一つとしてこの曲は演奏されているものと思われます。歌いこまれたヨーロッパの教会音楽の優れた演奏と思います。

聖処女 スタジオ・クラシック・シリーズ [DVD]
<奇跡の水>で有名な元祖スピリッチュアル・ポイント、フランスのルルド。実は4年ほど前に観光でこの地を訪れたことがあるのだが、いまだに(といっては語弊があるが)白衣姿のシスターやボーイスカウト少年が、重度の病や怪我を負った患者さんがのった車椅子を押している姿をいたるところで見かけたのを覚えている。街の中央にどでかい聖堂が建っていて、その広場で盛大なミサが開かれていた。
アカデミー賞5冠を達成した本作品は、この<奇跡の水>が湧き出す泉を発見した聖女ベネディット(ジェニファー・ジョーンズ)の半生を描いた1本だ。貧しい家に生まれたベネディットは妹たちとある日薪拾いに出かける。体が弱いベネディットが川の手前で妹たちを待っていると、なんとそこに貴婦人(聖母マリア)があらわれこの丘に毎日通ってくるように告げる。その噂はたちまち街中に広まり役人や警察をまきこんだ騒動に発展。ベネディットの話に懐疑的な人々は「奇跡を起こして証拠をみせろ」と声高に叫ぶのだが・・・。
この作品はれっきとしたアメリカ映画なので、単純なカソリックのプロパガンダになっていない点に注目したい。むしろ、科学や法律を信奉する役人や医者vsベネディットの奇跡を信じる民衆という構図に着目した社会派ドラマに仕上がっている。騒動で街への鉄道敷設が中止になることを恐れた役人連中が、あの手この手でベネディットを“嘘つき女”に仕立てあげようとするシークエンスなどは結構エグく描かれており、教会が政治案件として関わりをさけ中立的立場をとろうとするところも面白い。
結局は、彼女が掘り当てた水に病気を治癒する効用があることが発覚し、ルルドに各国から押し寄せる信者や患者の前に役人側が完敗をきっしてしまう。映画は、神父の勧誘によりシスターとなったベネディットのその後も描いており、乙女の純粋な信仰心が強調されたラストを迎える。水の効用については定かではないが(実際に飲んでは見たが・・・)、ルルドの地で起きた<奇跡>を社会問題としてとらえた着眼点がすばらしい秀作だ。

マグダラのマリア―エロスとアガペーの聖女 (中公新書)
小学生低学年の頃、宗教の時間に、『ヨハネによる福音書』にあるこんな一節を聞かされた。
マリアが自身の髪の毛で、イエスの足に香油を注いで拭いた。
低学年の男児にとって、そのマリアの行為は理解の外にあったが、何やら得体の知れぬ感覚だけが強烈に残った。そしてこれが、マグダラのマリアのイメージと重なって、私の中に存在し続けることになる。
これが実は、マグダラのマリアを描いたものではなく、ベタニアのマリアという別人のものなのだと知るのに、その後随分の時間を要した。
サンタ・マリア・デラ・グラッチェ教会に描かれた「最後の晩餐」の12使徒の中のひとりが男性ではなく女性で、それがマグダラのマリアではないか、という『ダヴィンチ・コード』の展開は、多くの人に衝撃を与えただろう。
ただ、私は、衝撃より前に「娼婦マグダラのマリアがなぜ?」という疑問を強く感じたのだが。
本書は、「聖女マグダラのマリア」が「娼婦マグダラのマリア」にそのイメージを変貌させていく過程を、聖書に入れられなかった外典の記述や修道会の存在、あるいは、多くの絵画、文学を網羅して描いてみせる。
マグダラのマリアとは何者だったのか?外典に見えるペテロの言動には、後のローマカトリックの展開を考えるとき、興味深いものがある。







