
方丈記私記 (ちくま文庫)
著者自身の昭和20年3月の東京大空襲の体験の記述から始まり、それを「方丈記」中の天災・飢饉等の記述と重ね合わせる事によって、「方丈記」あるいは「鴨長明」の新解釈を試みたエッセイ(私事だけを書いたエッセイと作中で再三強調されている)。「無常感」と一括りにされる「方丈記」の著者長明を、徹底的な現実主義者と捉えた所に新規性がある。長明とほぼ同時代に生きた藤原兼実「玉葉」、藤原定家「明月記」との比較考証も面白い。
前半の著者の主張を要約すれば以下の二点であろう。
(1) 日本においては「無常感」という概念が時の為政者によって利用され続けて来た。大きな天災・人災による民衆の苦しみが、この「無常感」によって"いつしか"押し流されるという事を為政者は見抜いていた。
(2) 大きな天災・人災によって、日本全体が階級のない社会になるなら、いっそ快哉を叫びたい。
(1)は今回の東日本大震災にも言える事で、「無常感」という言葉・概念が日本人に与える意味を改めて考えさせてくれる。(2)は多分に思想的色彩が濃い物で、戦時中には言えなかった事をドサクサまぐれに言い放った感がある。
後半は長明により迫って行くのだが、"贔屓の引き倒し"的記述が多く、その論には余り信が置けない。ただ、「方丈記」を「住」の書と捉えている点には首肯出来るものがあった。全体として、「方丈記」の再評価という点で価値がある書だと思う。
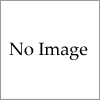
日本合唱曲全集 團伊玖磨作品集
久しぶりにCDラックから引っ張り出してみた。
岬の墓は10分以上かかる当時としては長い曲なので、
歌う立場としてはテンションを保つのが大変なのだが、なんか・・・途中で飽きてしまった。
筑後川、、、。今でも日本各地の合唱祭で「河口」は全員合唱で演奏されているのだろうか。
それだけだとしたらもったいない話だ。明確な構築性のある日本で最初の合唱組曲なのだから。
大地賛頌も似たような扱いを受けているのだろうか。
いまさら土の歌を定演でやるのもなあ・・・という声が聞こえてきそうだ。
海上の道、、、。録音が旧いのは仕方がないとして、作品自体も風化しつつあるような気がした。
辻先生も團先生も既に物故し随分と経つ。
聴き終えてから、懐かしいような、むず痒いような不思議な感覚が残った。
もう少し経ってからまた聴いてみようと思う。また新たな発見があるかもしれないから。
収録曲の生演奏に触れる機会は、おそらく今後殆どないかもしれないから。

時代の風音 (朝日文芸文庫)
専門分野の異なる3名による対談のため、各人の得意ジャンルにおける深い作品性や重さを期待すると喰い足りない感じがするのは否めない。特に宮崎氏は畑の違いからか年輪の差か進行役的立場からかやや影が薄い。ただ、逆に分野の違いから導かれる切り口の面白さや溜飲の下がる部分も多く、広範な話題や発言の端々にそれぞれの社会観・歴史観のようなものも見え隠れする。3名の肯定的(共感的?)・かつ思い入れの強すぎない読者・視聴者向け。他の著作の間に一冊この本もあると番外編的に楽しめる。サクサク読めてしまうテンポは単純に歴史文化系放談風読み物として見てもいいような気もするが、やはりヨソとはサイズがひとつちがうスケールがどことなくにじむ。個人的には、司馬氏のエッセイ作品の読者層あたりがなじみやすい内容な気が。文庫で読む分には充分なコストパフォーマンスかと。

日本合唱曲全集「岬の墓」團伊玖磨作品集
数ある團伊玖磨の合唱曲のなかでも「岬の墓」は屈指の名曲である。
この曲の歌詞は、船出する美しい船を岬の白い墓が見守る、という単純かつ和やかなもので、
十分ほどの演奏ながら、曲調は非常に変化に富んでいる。
男声部のやや低めで印象的なハミングのメロディから始まり、
その後は「今、過去、未来」を順に見つめるように、明瞭に曲の雰囲気が変化していく。
現代日本の合唱曲にしては古典的なクラシックらしい曲の構造を持ち、
安定感と荘重さにおいては、おそらく他の合唱曲の追随を許さないであろう。
辻氏が指揮するクロスロード・アカデミー・コーアの演奏は、人数編成は多くも少なくもないものの、
表現の豊かさと演奏の一体感において、とても素晴らしいものを聴かせてくれる。
このCDにはほかにも定番曲の「河口」も入っており、申し分ない内容と言える。









