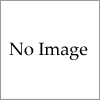
デマレ:グラン・モテ集
デマレは、ラモーが現れるまでのフランスで、最も個性的な作曲家であるといわれている。
若い頃デマレは、そこそこのキャリアを築いていたのだが、駆け落ちしたために、未成年者誘拐罪で死刑判決を受け、フランスに帰ることままならず、各国を渡り歩いた。皮肉にもその結果としてデマレは、音楽様式に各国ごとに非常に特徴のあったバロック時代において、各国の音楽語法を吸収した貴重なフランス人作曲家となったのである。
遍歴の最後、ロレーヌ(当時は独立を主張していた)にいたころのデマレが、頑なに恩赦を許さないルイ十四世に向けての一種の音楽による嘆願状として作曲した4曲のグラン・モテのうちの3曲がここにおさめられている。非常に表出的で、ドラランドなどのグラン・モテの様式美を重視したものとは大きく違う。しかし、2重フーガや時には10声にもなる対位法など、作曲技術は高度である。
「主よ、激しくとがめないでください」の歌詞に当時作曲したのはデマレだけだという。当然、ここでの「主」は、フランスにおいて神を代弁するルイ十四世を指すのだろう。この曲の他も、高度な作曲技術と表出性の高さは「主よ、いつまで」と「主をほめたたえよ、イスラエルよ」も同じである。
クリスティの演奏で気になったのは、いつもほどの冴えがないように感じられたことだが、競合盤(K617レーベルのクリストファー・ジャクソン指揮の4曲入った2枚組)よりはかなりレベルの高い演奏には違いなく、フランス・バロックには異質な曲想のため、そう感じるだけかもしれない。デマレは、海外盤では他の曲も出ているので、これを聴いて気に入った方はどうぞ。

失われたミカドの秘紋 エルサレムからヤマトへ 「漢字」がすべてを語りだす!
皇室の由来、国家神道のもとをユダヤ民族と繋げて論じる仮説がある。本書もそれを踏襲しているが、途中で中国・西域を挟んでいるのが新鮮か。小説の形をとっているため、荒唐無稽な感じが緩和されるが、これは論として出すには日本ではまだ抵抗が多いのだろうか(著者はそれを示唆しているが)。

エルサレム [DVD]
19世紀、スウェーデンの農村に、キリスト教原理主義が浸透し、古い信仰に支えられたこれまでの共同体が崩壊していきます。新しい信仰に救いを求め、神の都エルサレムを目指す者も、古い信仰と生まれ育った土地を愛してスウェーデンに残る者も、どちらも誠実であるがゆえに、親子、兄弟、恋人が決裂していきます。
主人公イングマルのその時々の決断と、その決断にいたるまでの苦悩を、もう少し丁寧に書いて欲しかった気はしますが、雪に覆われ、生きていくのが困難なスウェーデンと、たどり着いてみれば決して楽園ではなかった灼熱のエルサレムの自然、そして、それぞれの地で奇麗事ではない生を生きぬく人々が、圧倒的な美しさであらわれています。

スウェーデンボルグの霊界日記―死後の世界の詳細報告書
訳編者は本書の他にもいくつかのスウェーデンボルグの研究書を出版し、日本でのスウェーデンボルグ研究の第一人者であることは間違いない。研究書スウェーデンボルグの宗教世界―原宗教の一万年史スウェーデンボルグの思想―科学から神秘世界へ (講談社現代新書)はどれも秀逸で、この18世紀の人物が、ユダヤ・キリスト教の霊統のまさに「アンカー(最後の預言者)」であり、またその枠組みを超えて、太古からの人類の精神性の進化を解明する可能性を秘めた存在であることを常に意識しながら研究成果を発表している。また、訳編者は、本書のあとがきでも述べているとおり、スウェーデンボルグが単なる「霊視者」ではなく、17世紀以降の近代科学がさらに円熟した18世紀の「啓蒙の時代」の最新科学の言説体系を巧みに操れる一級の科学者・エンジニアであることを強調する。スウェーデンボルグが霊界・天界で観たものを記述する際、それは宗教家が自分の構想力に任せて儀礼的な常套句をちりばめるのではなく、優秀な建築技師が街中を移動中にある建物の構造を観たままにサラサラとスケッチするかのごとく、客観的かつ要点に絞った記述をしていることを念頭に置いて翻訳している。今の自分には理解・記述できないもの(あるいは、書き残すことを禁じられたもの)をそのままに残し、その欠けた部分を想像力で膨らませることはしない「科学者としてのスウェーデンボルグ」の息遣いまで聞こえてきそうな労作である。
ある程度スウェーデンボルグの著作に親しんでくれば、訳編者が苦心している以上の点は本書を読む内に十分伝わってくる。だが、まだ馴染みの浅い読者には、行間に隠れている「スウェーデンボルグが観ているもの」がイメージできないために、翻訳にその原因を求めてしまうのかもしれない。しかし、何冊かあるラテン語原典の邦訳書と比べても、本書の方が断然読み易く自然な日本語である。さらに、ラテン語邦訳群全体には、キリスト教系著作にありがちな、一部の日本人が感じるあの「バタ臭さ」がある。それとは対照的に、本書からは、読者がこの「キリスト教アレルギー」を起こしてスウェーデンボルグの著作を敬遠することがないようにとの配慮が感じられる。「1つでも多くの著作を原典から身近なものに」という、ラテン語邦訳者(故人)の永年の甚大な努力には最大の敬意を表したいが、本書訳編者と比べると、その見識の広さと成果物の質には明らかに開きがある。
このように本書をベタ褒めしてしまうと、私が訳編者本人であると思われては心外なので、以下、いくつかの注文:
1.この備忘録から敢えて取り上げ翻訳した箇所の選択理由が、「これ以上興味本位で取り上げるのはあまり意味がない」等、訳編者の独断・恣意的な印象を与えてしまっている。
2.文章中のイラスト・挿絵は不要では。読者なりの構想力、文章の内容から来る「照らし」を逆に制限してしまっている。
3.近年日本でも流行した心霊学・スピリチュアリズムとスウェーデンボルグの関連について、訳編者は敢えて距離を取り、感知しない禁欲的な態度に留まっている。その姿勢が翻訳の用語遣いにも現れており、この手の本を手に取る読者には、過重な読解作業を負わせる結果となっている嫌いがある。









