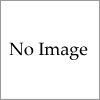日本の路地を旅する
これはものすごいルポルタージュだ。
筆者の文章が上手で、内面の部分は力強いが決して感情に流されることもなく、
また史実についてはわかりやすく的確に説明されているので まるで小説を読んで
いるかのように思えた。そう、なんだか「昔、われわれが子どもだった頃までは
こういったことがあったんだよ」という昔話のように見えてしまっている。
本当のところどうなんだろう。
そういった読後感を持つように意図的に書かれたのか、事実がそうなのか、それとも
著者がこの問題はもはやこうなっていて欲しいという願望なのか、それがわからない。
この本だけを読んで、この問題をわかった気になってはいけないのだろうと思う。
立場や考え方の違う人達それぞれの切り口で書いているので数冊読んでみたほうが
実際の温度がわかると思う。この本は比較的ドライだ。
後半部分で著者の心の奥での悩みが書かれているが、その分を表に出さないように、
著者は歯を食いしばって生きているように見える。だからウェットな部分を極力排除して
いるようだ。

疾走 上 (角川文庫)
家族、人と人とのつながりを一貫して書いてきた重松清が、
おそらく初めてそのすべてを断ち切った小説。この小説には一切の救いが、ない。
この小説は煉獄の人生を生きた15歳の少年の地獄の数年間を追った物語。
重々しく二人称で語られる体裁自体が重松作品の中では非常に異質で、発表時に騒然となったらしい。実際に読んでみて、問題作かつ衝撃作で各誌で絶賛されたのがよく分かる。
主人公は優秀な兄を持っていた。が、その兄がその集落で殺人を犯すよりも重い罪をおかしたことにより、歯車は狂いだす。家庭は荒れ、学校では極度ないやがらせにあい、親父は失踪し、母も壊れる。主人公は生きたい、それだけのために一人で大阪、東京へと故郷を出る。文庫本の裏表紙にある<孤独、祈り、暴力、セックス、聖書、殺人>という言葉の列挙がそのまま作品の内容だ。
普段の彼の作品ならば必ず「救い」は用意されている。もちろん安っぽい問題解決なんかはしない。けれども、作品の最後には何らかの、ほんとスイッチが入れ替わるだけのことだけど、それが一番の、救いが用意されている。今回はその一切を拒絶している。
突き放すように「おまえ」と語りかける様は異様で、何らかの作者の決意を意図しているようにも思える。クライマックスの間際に、語り部が誰にともなく弁解のように<わたしは、おまえの物語を語り続けてきた。おまえを救うためではなく、おまえを幸せに包み込むためではなく、だからわたしは、ひどく冷たい語り部なのだろう。>と付け足したように書かれている。ここが僕にとって印象的だった。なぜならここで著者は今までの著者自身に背を向けたから。
読めば分かる。そして、同時にこの作品から「重松清」を知ってほしくないとも、思う。
重松清は直木賞を受賞した時に自分で自分を分析していたのが印象的だった。「僕は文学を書けない」的なことを言っていて、その理由は「ひとり」になれない人間だから、と。「文学」とは孤独で「ひとり」の人間が共同体からはぐれて、それでも自分を表現することによって自分の存在確認、存在証明をすることによって生まれるものだと。いつも分岐点で一般人との最大公約数を選んできた自分には無理だ、とも同時に言っていたのだ。
また、「文学の資格」についても人一倍考えている人だ。自分にその資格がない以上、文学への畏怖とそれを書ける人への畏敬の念が強いらしく、自分を絶対に文学者とは軽々しく名乗らない。そして、やはり中上健次を別格のように尊敬している。早稲田文学時代に世話になったというだけではない「何か」を中上に与えられ、求められたのだとエッセイの数々を見れば気付く。そして中上文学を愛している人ならば「疾走」が重松清の中上健次へのオマージュであり、「挑戦」だということに気付く。そして、その挑戦は勝ったかどうかは僕には評価できないけれど、決して負けていない。見事に戦い抜いている。「ひとり」に苦しんで誰かと「ひとつ」になりたい孤独な主人公を最後まで描いている。
繰り返し、繰り返し、物語の中で「ひとり」「ふたり」「ひとつ」という言葉は踊り、うねる。
この作品は徹底した救いのない物語で、ここまでの覚悟で書いたからには安易な救いなんかは書いてほしくなかった。だから、物語の終着点はすごく満足だったし、目頭があつくなった。救いはなくても望みはあるんだな、と思えるものだった。
僕はひさしぶりに小説を「取り憑かれたよう」に読んだ。おそらく作者も「取り憑かれたよう」に小説を書いたんじゃないだろうか。「疾走」というタイトルは走ることに特別なものを感じ、生き抜こうとし、クライマックスでも文字通り駆け抜けた主人公を意味しているだけではなく、それを図らずと意味しているんじゃないかと思う。
最後まで自分勝手な書評だなと思うけれど、僕のように「ひとり」で生きられずに最大公約数を選んできた者の言葉などこんなものだと分かっている。それでも良いと思って書いている。

枯木灘 (河出文庫 102A)
レビューにも日本文学の最高傑作と書かれている方があって、それならばと読んでみたのだけれども、確かにものすごい完成度の高い作品だと思う。自分の中では今まで読んできた小説の中では絶対にベスト3には入る。ただの近代私小説よりは構成でも印象でもこの本の方が格段に上だ。
所謂性とか暴力、複雑な血縁関係の中から生じる苦悩などを描き出した作品。複雑、と言っても一通りでなく、従来のメロドラマの離婚・不倫・妾の子などが何重にも重なっており、ほとんど網のになっている。そこから感じる苦悩や、兄弟内の事件、自分の本当の父の肖像などが何度も繰り返し(くどいほど)語られ壮絶な中に生きる主人公の姿が目に見えてくるようだった。すべてを忘れるために土方作業に打ち込む時の鮮烈な描写も忘れられない程インパクトが強い。主人公のやりようの無い思いも簡潔な文章でありながら、ひしひしと伝わってくる。
似た様な小説は石原慎太郎氏なども書いているが、血縁関係などをからませる中上健次氏の文章の方が私は好きだし、印象深いと思う。日本人必読、とはさすがに言わないけれども、日々の生活に不満や憂鬱を感じている人などには同感できるのではないかと感じた。興味がある人は勿論読んでみるといいと思う。

青春の殺人者 デラックス版 [DVD]
受験浪人生が金属バットで親を殴り殺す、という日本の戦後で初めての親殺しという衝撃的な事件(今や日常茶飯事で衝撃もなかろうが)が起きたのはちょうど、この頃だった。
1976年のキネマ旬報日本映画1位となった作品。長谷川和彦監督はデビュー作にしていきなりの1位という史上初の快挙。小子はそのキネ旬表彰式(77年の2月頃。於:千代田劇場=日比谷映画街にあった)で見た。それ以来は一度も見ていない。本DVDも未購入。時に16歳。今なら入場制限が付くはずで、実際この年齢の人間にはかなり衝撃的な映画ではあった。が、それ以上に表彰式での出来事がこの衝撃以上に忘れられない。
当時のキネ旬・白井佳夫編集長解任劇を巡る抗議グループがこの日、場内の主要席に陣取り、会場内に怒号の嵐が渦巻いた事件だ。突然の出来事に何のことかわからない本作の主演女優賞(『大地の子守歌』も対象)だった原田美枝子さんは、終始ほとんど半べそ状態だった。
白井氏の解任理由は確か、ルポライターの竹中労の連載が突然、中止されたことに端を発したものらしいが、詳しくは忘れた。だいたい竹中労が何で映画のこと書くのかわからんが、それで解任した側というのもふるっていた。当時のキネ旬の発行人は金森子鉄という人物。いかにも怪しげな名前だが、実はこの人、最後の「大物総会屋」と言われる人物であったことがその後何年も経ってから明らかになった(といっても本人はそうじゃないと否定していたが)。どういう経緯でこの人が日本で最も権威のある映画批評誌とされていた雑誌のオーナーになれたのかは知らない。恐らく、大手映画会社の株をたくさん持っていたことから、その株とのバーターで経営権を手に入れたのではないかと想像する。
どだい興行の世界は昔からアングラが関係しているのは知れた事実。今から思えば、当時この雑誌に寄稿していた高名なる日本のほとんどの映画ひょうろん家氏は、結局のところ、ソーカイヤからお金もらっていただけ、ということになるので、ちょと衝撃的な事実ではあろう。
今やレビューなどは素人がこうやって(と言っても自分はリアルの世界ではプロのライターだが)無償で書くべきものになりつつあるから、偉そうなひょーろん家先生のレビュー行為がだんだんと無効化されていくことはたいへんよろしいことだとは思う。